NIDSコメンタリー 第316号 2024年5月14日(特集:「新領域の安全保障」 vol.2) 脅威インテリジェンスの機能的・歴史的視座 民間セクターにおける共有エコシステム分析と公共セクターの関与について
- 東京海上ホールディングス株式会社 IT企画部 Lead Cyber Security Architect
- 石川 朝久
はじめに
脅威インテリジェンス(Cyber Threat Intelligence)は、脅威に対する情報を収集し、サイバー防御に活用する技術で、民間セクター(民間企業)を中心に積極的に活用されている。一方、脅威インテリジェンスのエコシステムにおいて、公共セクター(政府機関)の関与は限定的である場合が多い。
本論考では、脅威インテリジェンスの利活用と公共セクターの関与について、3つの側面から分析を行う。第一に、脅威インテリジェンスの役割や位置づけについて、理論的整理を確認する。第二に、機能的視座として、脅威インテリジェンスのステークホルダーを洗い出し、目的・役割を提示することで、利活用のエコシステムを分析する。そして、どのようなインセンティブに基づいて活動しているか、なぜ公共セクターの関与が少ないのか、考察する。第三に、脅威インテリジェンスの歴史的変遷に焦点を当てる。脅威インテリジェンスは、伝統的なインテリジェンス技法を拝借しつつ独自の進化を遂げており、歴史を紐解き、現在の立ち位置を分析する。
脅威インテリジェンスの基礎理論
最初に、脅威インテリジェンスの基礎理論の概略1を示し、議論の共通知識を整理する。
脅威インテリジェンスの基礎理論
定義を紐解くため、「脅威」と「インテリジェンス」という2種類の用語に分解して解説する。
脅威(Threat)とは、様々な意味・文脈で利用されるが、米国のセキュリティ研究教育機関SANS Instituteの定義2によれば、①意図、②能力、③機会の3要素が備わった状態を脅威と定義しており、当該脅威となる個人・組織・グループを攻撃グループ(Threat Actor)と呼ぶ。第一に、意図(Intent)とは、攻撃グループが攻撃対象組織を狙う目的・動機を意味する。Microsoft3は、イランの支援を受けたMint Sandstormが、大学や研究機関で中東問題に取り組む研究者を標的として、情報収集していると報告した。第二に、能力(Capability)とは、目的を達成するために必要な攻撃者の能力・攻撃手法を意味する。前述の例によれば、評判の高い報道機関のジャーナリストを装うソーシャルエンジニアリング、レジストリキーを利用した持続性確保、カスタムバックドアMediaPIの利用などが該当する。また、Open AIとMicrosoft社の共同調査4によれば、昨今の攻撃グループは大規模言語モデル(LLM)を活用していることも知られている。第三に、機会(Opportunity)とは、攻撃を可能とする環境・条件を意味する。前述の例でいえば、攻撃者は、なりすましたジャーナリストの個人メールに類似したメールアドレスを使用し、イスラエルとハマス戦争に関する記事について意見を求める無害な電子メールを送り、信頼関係を事前に構築した。これにより、標的型フィッシング攻撃が成立しやすかったことが挙げられる。
一方インテリジェンス(Intelligence)とは、シャーマン・ケントが著書5で「インテリジェンスとは知識であり、組織であり、活動でもある」と表現した通り、インテリジェンスの定義6には①成果物、②プロセス、③組織の3種類がある。具体的には、インテリジェンスサイクル(方針策定→収集→加工→分析→配布)に従い、収集したデータからインテリジェンスを生成する。上記の定義から、脅威インテリジェンスとは、「(サイバーセキュリティの)脅威に関する情報について、収集・加工・統合・評価・分析・解釈を行った成果物。あるいは、当該成果物を作成するためのプロセス・組織を指す」と定義される。
脅威インテリジェンスの目的
脅威インテリジェンスの目的は一般に、より高度な「セキュリティリスク管理」のためとされている。前述のSANS Instituteの記事によれば、サイバーセキュリティリスクは、以下の方程式で成立する。
一般に「脅威」は、様々なセキュリティ対策に保護された「資産」を狙う。そして、セキュリティ対策に「脆弱性」がある場合、資産を破壊したり、盗み出したりすることが可能となり、リスクが発生する。重要な観点として、防御側としてコントロールできる要素は「脆弱性」と「資産」に限定される。そのため、伝統的なリスク管理手法では、できる限り「脆弱性」をつぶし、安全な場所で「資産」を保有することが重要であるとされてきた。しかし、その伝統的なリスク管理手法も成立しなくなっている。その理由は様々であるが、データの増加、攻撃対象領域の拡大、技術的負債やサーバの増加、利用製品の多様化、クラウド活用やリモートワークの普及、サプライチェーンリスクの台頭など、管理負荷・難易度が増加していることが挙げられる。一方、サイバーセキュリティへのリソース(ヒト・モノ・金・時間)は限られており、全方位的な対策を行うことは現実的ではない。そのため、リスクの優先度をつけるために「脅威」に着目する脅威インテリジェンスが注目されている。「敵を知る」ことで、具体的な脅威へ対応することを優先する脅威ベース型リスク管理手法が主流となりつつある。
脅威インテリジェンスの分類と良いインテリジェンスの要件
脅威インテリジェンスは、ステークホルダーに利用され、初めて価値を持つ。そのため、種類とその目的を理解することが重要となる。図1に、その分類を示す。
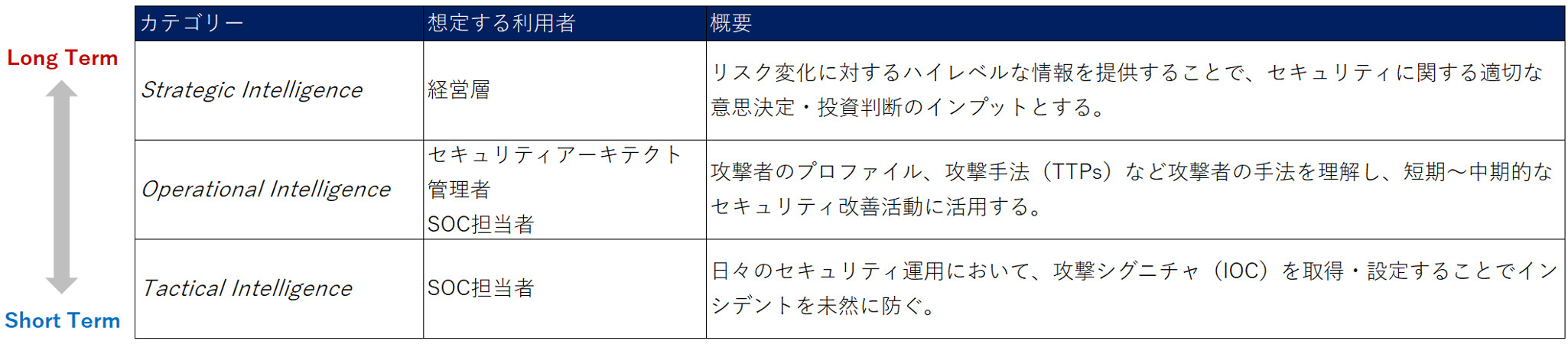
図 1 脅威インテリジェンスの分類
また、脅威インテリジェンスが有効活用されるためには、①正確性(Accurate)、②利用者目線である(Audience Focused)、③アクショナブル(Actionable)、④適切なタイミング(Adequate Timing)の4A条件を満たす必要がある。図2にその概要を示す。
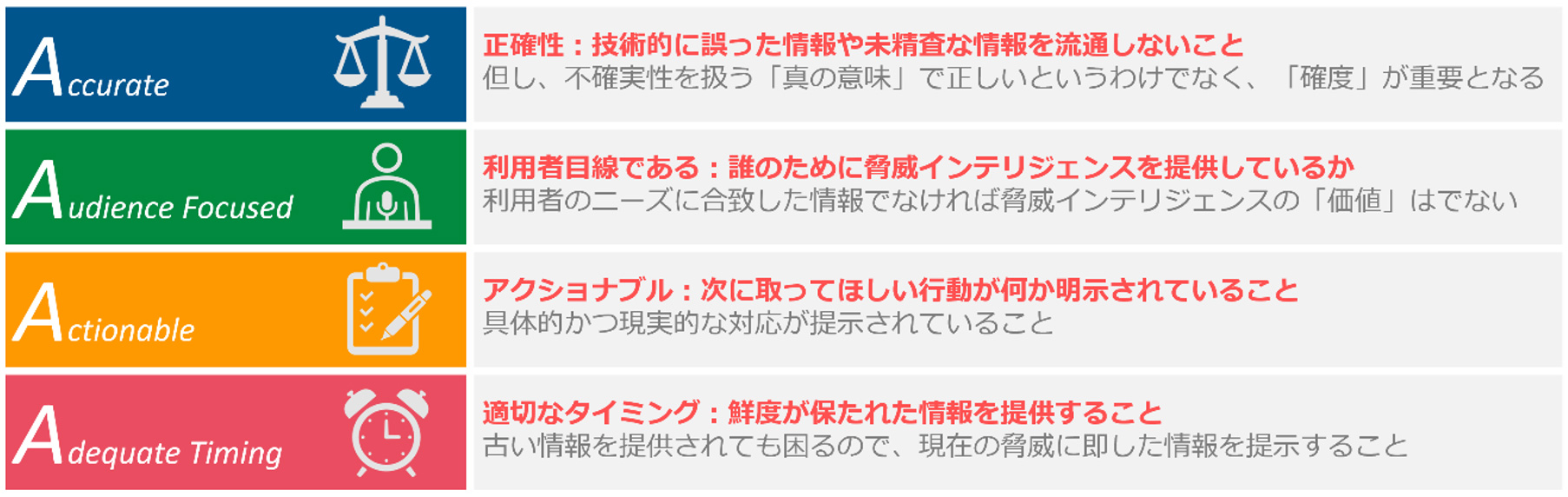
図 2 脅威インテリジェンスを有効活用するための4A条件
脅威インテリジェンスの機能的視座:民間セクターにおける独自の進化
民間セクターでは「脅威」への分析技術を高度化するため、国のインテリジェンス機関が持つ技術・思考方法を借りつつ、サイバー領域へ応用してきた経緯がある。その具体例として、インテリジェンスサイクル、あるいは『The Red Team Handbook - The Army's Guide to Making Better Decisions』7で紹介されている競合仮説分析、批判的思考などが挙げられる。また、元米国空軍士官であるKevin Mandia氏が創業したMandiant社は、2013年に中国人民解放軍が米国のサイバー攻撃に関与していることを示したレポート『APT1 - Exposing One of China’s Cyber Espionage Units』8を発表したが、伝統的なインテリジェンス技法がサイバー領域にも有効に活用できることを実証した事例と言える。加えて、脅威に最も携わるであろうDFIR(Digital Forensics & Incident Response)の専門家に、米軍・警察経験者が多数いたことも、伝統的なインテリジェンス技法を受け入れる上で下地になってきたと推察される。一方、国のインテリジェンス機関の技術・思考法を利用してきた民間セクターにおいて、脅威インテリジェンスは独自の進化・活用を遂げてきた。その理由を3種類の観点から紐解いていく。
理由1:目的の相違
第一に、インテリジェンスを必要とする目的の相違である。伝統的なインテリジェンスは国防を目的に収集され、国家の専権事項である。一方、サイバー攻撃において、民間セクターが「脅威」を分析する理由はあくまで「リスク管理」であり、漏洩・攻撃・侵害を防ぐことが主眼である。国防の文脈でも、脅威インテリジェンスの文脈でも「脅威の排除」という用語は登場するが、民間セクターにとっては予防活動、被害を最小化・極小化する検知・対応活動を意味する。一方、国防を担う公共セクターにとって、「脅威の排除」とはより広い意味で利用されている。そのため、サイバー攻撃を受けた場合、公共セクターと民間セクターにおいて脅威インテリジェンスに対する関わり方は異なる。
その一例として、アトリビューション分析9を取り上げてみたい。アトリビューション分析とは「攻撃グループを特定する技術」であり、図3で示したC4モデル10はアトリビューション分析プロセスと実施レベルを示した図である。

図 3 アトリビューションプロセスモデル(C4モデル)と実施レベル
横軸がアトリビューションの実施プロセスを意味›し、収集→ クラスタリング→ 告発→ 情報の提供の流れで実施していく。一方、縦軸は実施レベルを意味する。実施レベルは、「攻撃キャンペーン」と呼ばれる攻撃パターンを特定するレベルから、攻撃グループの動機、攻撃者の特定に至るレベルまである。民間セクターと公共セクターが必要とするインテリジェンスに注目した場合、民間セクターの多くは「侵入セット・攻撃キャンペーンの特定」を必要とする。攻撃パターンがわかれば、自社環境への影響を分析し、予防・検知に役立てられるため、「リスク管理」に役立つアクショナブルな情報である。一方、動機・攻撃グループの属性情報は、民間セクターにとってはアクショナブルな情報ではないが、国防を担う公共セクターの観点では脅威動向や政策を反映させる上でアクショナブルな情報であると推察される。言い換えれば、アトリビューション一つに着目しても、公共セクター・民間セクターで必要とする情報には差異があり、利活用の差に表れている。
理由2:調査主体・調査対象の相違
第二に、調査主体と調査対象の違いである。例えば、エスピオナージの場合、調査主体は警察・防諜機関であり、民間セクターの事案でも、捜査、取り調べ権限、鑑識技術などは法的・技術的制約から国家の専権事項である。あるいは、重要インフラでの攻撃が発生した場合、自衛隊が衛星写真・レーダーを活用して対応する点で同様である。一方、民間セクターがサイバー攻撃を受けた場合、民間セクターがセキュリティベンダーと協力しながら調査を行うことが一般的である。例えば、情報漏洩事案の場合、被害者や関係省庁への報告など民間セクターとして説明責任を果たす必要があること、予防・検知・対応に対する再発防止策を実装し、事業継続を行うといった目的があるため、デジタルフォレンジック技術を活用して、端末・サーバに残された痕跡・ログの分析を行う。言い換えれば、調査主体・調査対象が民間セクターに閉じる傾向にあったため、得られる脅威インテリジェンスも民間セクター内で流通し、独自に進化を遂げた傾向がある。
理由3:共有インセンティブの相違
民間セクターが脅威インテリジェンスを共有する際、インセンティブが大きく影響する。図4は、横軸に共有、公表、報告・連絡11を取り、ステークホルダーをマッピングした。そして、民間セクターが作成した脅威インテリジェンスを共有する際のエコシステムと課題を表現した図である。
以後、図4で整理した3種類の論点について議論していく。
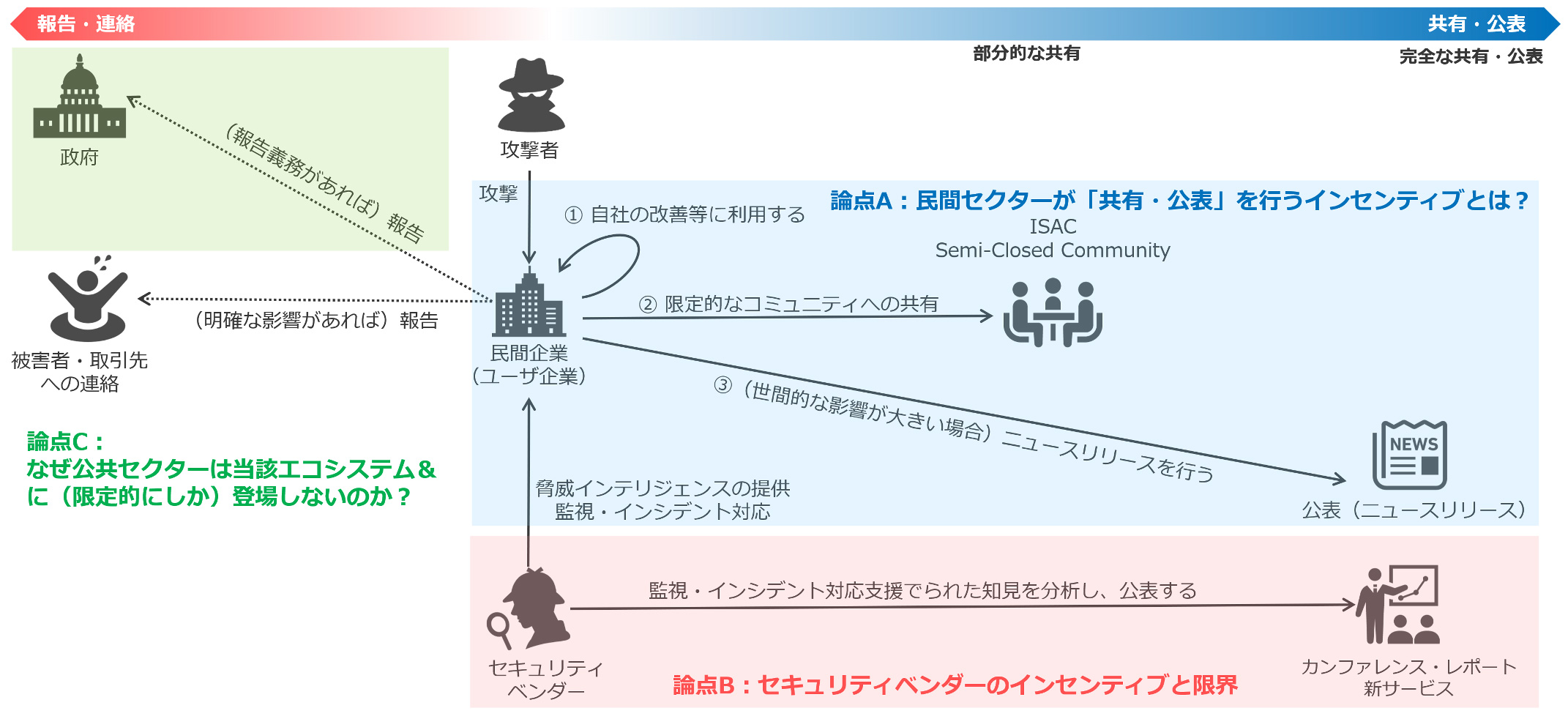
図 4 民間セクターを中心とした脅威インテリジェンス共有のエコシステムと課題
論点A:民間セクターが「共有・公表」を行うインセンティブとは?
一般に、インシデント発生時において、(セキュリティ製品の導入・運用などの)①予防コストに加え、(分析・対策など)②検知・対応コストを支払う必要がある。また、「共有」を行う際には、既に示した4A条件を満たした上で、「誰にどこまで何を開示するのか?」を考えなければならず、③共有コストは大きい。また、共有後、意図しない形で情報が伝播してしまうリスクがある、更問が行われるなど様々な④追加コストが発生する。一方、各組織が共有を行う際には、当該コストの総量よりも「共有するメリット」が大きい必要がある。しかし、共有を実施しても「フリーランチ」の提供となる可能性、そもそもネガティブな情報を出したくないなど、「共有するメリット」が上回るケースは少ないと推察される。
一方、筆者の在籍する金融業界では金融ISACなどのコミュニティが成立し、「共助」を実践している。その背景には、インセンティブ設計にも様々な施策が取り入れられていることが挙げられる。まず、左辺に注目すると、共有範囲・共有内容が定式化されており、③共有コストが低減されている。また、コミュニティによる秘密保持、TLPプロトコル、善意での活動であることが徹底されており、④(共有に伴う)追加コストが増加しない工夫がされている。次に右辺に注目すると、「共有するメリット」についてコンセンサスが取られている。同じ業界であれば、直面する脅威や攻撃グループ、悪用される攻撃手口も同様である一方、(異なるテレメトリ、リソース、キャパシティ、偶然性など)脅威情報を網羅的に収集できる組織はないというコンセンサスがある。そのため、「共助」として情報を共有することで、自社では把握できない脅威の全体像を把握できる長期的なメリットがあり、潜在的な脅威を排除することが可能となる。また、この「共助」により、②検知・対応コストを低減することにもつながっている。
また、内在的な論理としてマタイ効果(Matthew Effect)を指摘しておきたい。マタイ効果とは、1968年に科学社会学者ロバート・キング・マートンによって提唱された考え方で、「条件に恵まれた研究者は優れた業績を挙げることでさらに条件に恵まれる」という現象を説明した概念であるが、情報共有コミュニティにおいても、「情報共有した組織に、より多くの情報が集まる」効果は実務でも多く観察される。
論点B:セキュリティベンダーのインセンティブと限界
セキュリティベンダーは、自社技術力のアピール、サービス開発への活用、製品に対するニーズ構築のため、共有には積極的である。一方、ベンダーが提供するインテリジェンスの課題を列挙する。
第一に、情報粒度である。被害企業から見れば、サービス利用に必要な情報を提供しているだけであり、ベンダーが取得できる情報は技術的情報に限られる。それゆえ、能力については分析できるが、意図・機会に関する十分な分析は難しいと推察される。また、詳細情報を開示できないケースも多く、情報粒度も汎化された内容となる。
第二に、ベンダーが取得するデータのカバレッジである。ベンダー間での情報連携はほとんど行われず、自社のサービス・製品で取得できるデータに基づいて分析される。言い換えれば、当該ベンダーの観測範囲で分析・解釈された結果であるため、偏り等を踏まえて取り扱う必要がある。
第三に、ベンダーの脅威インテリジェンスが、本当に「正確な」情報なのか、検証する術がないという問題である。ここでいう「正確性」は、データセットが公開されないため、情報の受け手として、自組織との関連性・影響度を自身で検証することが難しいという意味である。
論点C:なぜ公共セクターは当該エコシステムに(限定的にしか)登場しないのか?
公共セクターがエコシステムに限定的にしか登場しない理由は、インセンティブの不一致と考えられる。まず、公共セクターへの報告に対し、一定のハードルがある。また、公共セクターが脅威インテリジェンスを必要とする理由は国防のためであるが、アトリビューション分析を含め、「第5の戦場」と呼ばれるサイバー空間において、公共セクターが観測可能な「レーダー」は限定的である。言い換えれば、公共セクターだけで情報収集を完結することは難しく、民間セクターで受けた攻撃等をメタ分析することが現実的である。一方、民間セクターからすると、情報提供のハードルが高いこと、当該情報を公共セクターに提供しても4A条件を満たすインテリジェンスが作成されるまでには時間がかかる可能性があるなど、提供へのメリットが見えづらく、インセンティブの不一致が発生していると推察される。
脅威インテリジェンスの歴史的視座
最後に、脅威インテリジェンスの米国産業界における歴史に焦点を当て、その変遷を分析する。(所説あるが)世界で初めて行われたサイバー脅威インテリジェンス活動とは、『カッコウはコンピュータに卵を産む』12という小説という形で描かれた、1980年代半ばの実話だとされているが、米国産業界の変遷を理解することで、日本の脅威インテリジェンス動向がどの段階にいるか分析する。北米における脅威インテリジェンスの歴史的変遷は図5で示す通り、4種類の段階で説明できると考えている。
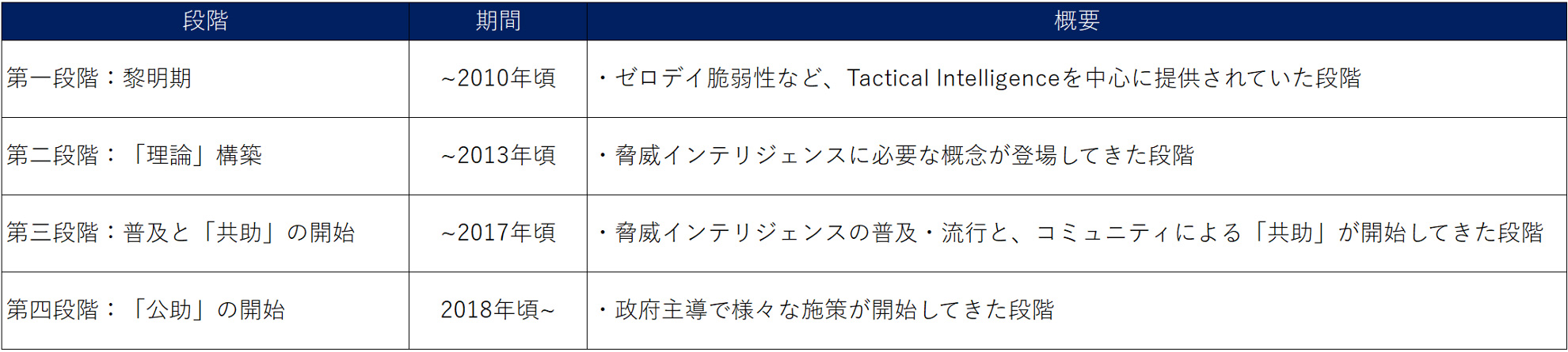
図 5 脅威インテリジェンスの歴史的変遷
第一段階: 黎明期
2010年頃までを黎明期とする。この時期には、「脅威インテリジェンス」というキーワードは登場しているが、その多くがゼロデイ脆弱性などの脆弱性情報、攻撃元IPアドレスなどを中心とした脅威インテリジェンス、現在でいえばTactical Intelligenceが主に利活用されていた。
第二段階:「理論」構築
2013年頃までは「理論」構築の時代であり、脅威インテリジェンスに必要な概念が登場している。例えば、脅威インテリジェンスでは重要なキーワードであるIOC(Indicator of Compromise)13、MITRE ATT&CKフレームワーク14、Pyramid of Pain15(痛みのピラミッド)といった概念が整理され、実践するツール16が登場したのもこの時期である。また、前述で紹介したMandiant社のAPT-1レポートが登場したのも2013年度であり、理論の提唱とその実践が行われた時代である。
第三段階:普及と「共助」の開始
第三段階は、2017年度頃までを指す。この頃から、第二段階で登場してきた概念を利用し、脅威インテリジェンスの作成・活用方法が定式化され、脅威インテリジェンスが流行・普及した時期である。実際、各種書籍やトレーニングなどが多数登場したのもこの時期である。
また、同時にコミュニティによる「共助」が開始した時期でもある。2015年度に米国にてCybersecurity Information Sharing Act17が議会で承認され、官民で情報共有する枠組みが定められたこともあり、ISACを含む脅威インテリジェンスコミュニティ18が形成され、脅威インテリジェンスを利用・交換する組織がより活発に活動し始めた時期である。一方、当時筆者は米国に滞在していたが、脅威インテリジェンスの活用ブームの裏で、脅威インテリジェンス「疲れ」などの声も出始めてきた時期でもある。
また、アトリビューション分析に関する議論が活発に行われた時期でもある。2016年は、ドナルド・トランプ氏が第45代米大統領に就任した歴史的な大統領選挙であったこともあり、当時はサイバー攻撃による選挙介入も話題になっていた。その一例として、DNC(Democratic National Committee)に対する攻撃がAPT28とAPT29による攻撃19だと発表され、各社が競うようにアトリビューションを行っていた。その一方、サイバーセキュリティのカンファレンスでは、こうしたアトリビューション分析に関して、False Flag(偽旗)である可能性を考慮すべきと示唆する発表20や、民間セクターは「アトリビューションをする必要がないのではないか?」といった指摘21が行われている。言い換えれば、脅威インテリジェンスに対する各ステークホルダーの役割・線引きが行われ、アトリビューションの有効性なども指摘されていた時代である。
第四段階:「公助」の開始
第四段階として、2018年から現在までを意味する。この段階は、「公助」の開始と位置付けられる。2018年には、CISA(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)22が設立され、KEV(Known Exploited Vulnerability)23やCybersecurity Alerts & Advisory24を発表にするなど、政府主導で様々な活動が行われている。また、各種政府機関も様々なガイドライン・ツールの公開25を開始している。その代表例として、NSAが開発したマルウェア解析フレームワークGhidra26があるが、他にも様々なツール27を公開している。また、2018年度以降、FBIでも積極的にAPTグループを”Cyber’s Most Wanted”28で名指ししている。
歴史的変遷からの考察
歴史的変遷からわかる通り、脅威インテリジェンス分野で進んでいる北米産業界でも、公共セクターがステークホルダーとして活動し始めたのは2018年前後である。米国でもCISAが設立されて以降、様々なレポート・ツールを公開するなど積極的な情報発信・共有を行っており、その存在感を示している。なお、「公助」においても、CISAのようなトップダウン型アプローチ以外にも、ボトムアップ型アプローチも存在する。その一例として、InfraGard29と呼ばれる組織が挙げられる。1996年にFBI(連邦捜査局)のクリーブランド支局におけるローカルな取り組みとして始まり、その後全米の支局に拡大された組織である。FBI、地方の法執行機関、民間企業や学術機関との連携、情報共有を目的としたプログラムであり、テロ、インテリジェンス、犯罪、サイバーセキュリティについて情報交換が行われている。サイバー犯罪やテロ対策などは、「官のみの対応で重要インフラを防護することは困難である」ことから生まれた組織であり、接点を増やすことにより公共セクターで取得可能な情報を増やす狙いがあると推察される。
一方、日本の状況を鑑みると、執筆時点で民間セクターでの脅威インテリジェンス活用が普及し、「共助」のコミュニティ形成が進んでいる。そのため、北米産業界の歴史に習うのであれば、第四段階である「公助」の支援に移行する時期であると推察される。
最後に
本稿では、脅威インテリジェンスの利活用、および公共セクターの関与が限定的である構造について、機能軸と歴史軸で紐解いてきた。機能軸から見てわかる通り、脅威情報を収集し、サイバー防御に活用する脅威インテリジェンスは、民間セクターで積極的に活用されている。一方、エコシステムからみると、目的・インセンティブの観点から、公共セクターの関与は限定的であることを指摘した。また、歴史軸からすると、日本は「共助」が進んできており、今後「公助」へと移行する可能性を指摘した。
様々な分析からみてわかる通り、公共セクターと民間セクターがそれぞれ脅威インテリジェンスに求める目的は異なる。そのため、情報の流通を活性化したり、情報に一定の品質を担保したりする目的で、公共セクターがエコシステムに関与することは重要だが、民間セクターと同じことをする必要はないと考えられる。むしろ、公共セクターが脅威インテリジェンスを必要とする理由は、政策・国防の側面が強く、当該目的に必要な情報を収集できる仕組み・態勢を構築することが重要であると考えられる。
ハイブリット戦など、国防の観点でサイバー攻撃が果たす役割は増えており、アトリビューション技術を中心に、脅威インテリジェンスはより重要な技術となる。本稿が、その一助になれば幸いである。
(2024年4月26日:脱稿)
Profile
- 石川 朝久
- 東京海上ホールディングス株式会社 IT企画部 Lead Cyber Security Architect
- 専門分野:
サイバーセキュリティ